2025~2026年シーズンは以下の3株がワクチン製造株として選定されました。
- A型株
-
- A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)
- A/パース/722/2024(IVR-262)(H3N2)
- B型株
-
- B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)
インフルエンザは、ただの風邪とは異なり、38℃以上の高熱や頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感といった症状が比較的急速に現れ、時には肺炎や脳症などの重い合併症を伴い、入院治療が必要になったり、死亡することもある病気です。ご自身と大切な方を守るために、インフルエンザ予防接種について正しい知識を持ち、適切な対策を講じることが重要です。
1. インフルエンザ予防接種、なぜ受けるべき?その効果とは
インフルエンザワクチンは、感染そのものを完全に防ぐ働きはありませんが、感染後に発症する可能性を低減させ、万が一発病した場合の重症化を防止する効果が報告されています。麻しんや風しんワクチンほど高い発病予防効果は期待できませんが、特に重症化予防において大きな効果が認められています。
- 高齢者の重症化・死亡予防効果 国内の研究によれば、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については、34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。
- 乳幼児の発病防止効果 乳幼児のインフルエンザワクチン有効性については報告によって幅がありますが、概ね20~60%の発病防止効果があったと報告されています。重症化予防に関する有効性を示唆する報告も存在します。
2. いつ接種するのが効果的?
接種してから、効果が現れてくるのには約2週間程度かかりますので、流行期の2週間前には遅くとも接種を終わらせておく必要があります。ワクチンの効果は約5ヶ月持続すると考えられており、10月に接種すると翌年2月までは効果が保たれると考えられます
3. 接種回数と対象者は?
インフルエンザワクチンの接種回数は、年齢によって異なります。
- 13歳以上の方:ワクチンの添付文書には「13歳以上のものは1回または2回注射」と記載されていますが、健康な成人や基礎疾患のある方を対象とした研究から、インフルエンザワクチン0.5mLの1回接種で、2回接種と同等の抗体価の上昇が得られるとの報告があります。ただし、医学的な理由により医師が2回接種を必要と判断した場合は、この限りではありません。なお、予防接種法に基づく定期の予防接種は1回接種としています。
- 13歳未満の方:2回接種が必要です。1回接種後よりも2回接種後の方がより高い抗体価の上昇が得られます。
- 6ヶ月以上3歳未満の方:1回0.25mLを2回接種(一部のワクチンは1歳以上3歳未満が対象)。
- 3歳以上13歳未満の方:1回0.5mLを2回接種。 (※1回目の接種時に12歳で2回目に13歳になった場合でも、12歳として2回目の接種を行って差し支えありません。)
定期接種の対象者
以下の方々は、インフルエンザにかかると重症化しやすく、インフルエンザワクチン接種による重症化の予防効果による便益が大きいと考えられるため、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象となっています。
- 65歳以上の方
- 60歳~64歳で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方(概ね身体障害者障害程度等級1級に相当)。
- 60歳~64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね身体障害者障害程度等級1級に相当)。 定期接種の対象者については、接種費用が市区町村によって公費負担されている場合もありますので、お住まいの市区町村(保健所・保健センター)、医師会、医療機関、かかりつけ医等に問い合わせていただくようお願いします。
4. 予防接種で心配な「副反応」について
ワクチン接種後に、体の中で免疫が作られる過程で様々な反応が見られることがあります。これらを「副反応」と呼びます。
- 比較的多く見られる副反応
- 接種した場所(局所):赤み(発赤)、はれ(腫脹)、痛み(疼痛)等。接種を受けられた方の10~20%に起こり、通常2~3日で消失します。
- 全身性の反応:発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)など。接種を受けられた方の5~10%に起こり、こちらも通常2~3日で消失します。
- まれに見られる重い副反応
- ショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、赤み、かゆみ、呼吸困難等)。これらはワクチンに対するアレルギー反応で接種後、比較的すぐに起こることが多いです。
- そのほか、ギラン・バレ症候群、急性脳症、けいれん、肝機能障害、喘息発作などが重い副反応としてまれに報告されています。 重要な注意点として、これらの副反応疑い報告において、死亡とワクチン接種の直接の明確な因果関係があるとされた症例は認められていません。死亡例のほとんどが、基礎疾患などがあるご高齢の方でした。 また、現在広く用いられている不活化ワクチンは、インフルエンザウイルスから免疫を作るのに必要な成分だけを取り出して作られているため、ワクチン接種によってインフルエンザを発症することはありません。
5. 予防接種以外のインフルエンザ対策も忘れずに!
ワクチン接種に加え、日頃から以下の対策を心がけることで、感染リスクをさらに減らすことができます。
- 外出後の手洗い・手指消毒:流水と石鹸による手洗いは、手指など体についたウイルスを物理的に除去するために有効です。アルコール製剤による手指衛生も効果があります。
- 適度な湿度の保持:空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。
- 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取:体の抵抗力を高めるために、日頃から心がけましょう。
- 人混みや繁華街への外出を控える:インフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
- マスクの着用:やむを得ず人混みに入る可能性がある場合には、ある程度、飛沫感染等を防ぐことができる不織布製マスクを着用することは一つの防御策と考えられます。
- こまめな換気:季節を問わず、十分な換気が重要です。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。窓開け換気の場合は、対角線上にあるドアや窓を2か所開放すると効果的です。
まとめ
インフルエンザ予防接種は、インフルエンザの発病リスクを減らし、特に重症化を防ぐ上で非常に有効な手段です。ご自身の健康を守り、周囲への感染拡大を防ぐためにも、ぜひ今年の冬は予防接種をご検討ください。
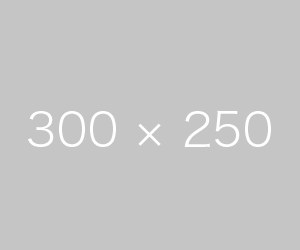
コメント